こんにちは、山田まみこです。
20代前半で海外起業し、現在も経営に携わっています。
ブログ『女社長の思考術』では、起業家としての経験や考え方
実践的なアイデアをシェアしていきたいと思います。
今日は、私が経験した具体例を通じて、アウトプットが持つ力と、
それによってどのようにインプットしたことが深まるのかを探っていきます。
先日、『行動には意味がある/朝礼を行う理由とその効果』というお話をしました。

「意図を持って行動しましょう」という話だったのですが、
今日はこの行動に関連して「アウトプットの重要性」について、
みなさんにシェアしたいと思います。
今日お話しする「アウトプット」も行動の1つです。
インプットとアウトプットの関係とは?
現代のビジネス環境や学問の世界で、情報をただ「インプット」するだけではなく、
それをいかに「アウトプット」していくかが、
自分の知識やスキルを真に身に着けるための鍵です。
インプットしたことは、それを自分の言葉で説明したり、他者に教えたり、
具体的な行動として表現することで、本物の知識として根付いていきます。
学ぶこと、経験することは、ビジネスにおいても自己成長においても重要な要素です。
まず「インプット」は、
自分に新しい知識や技術、情報を取り入れる行為を指し、これが学びの第一歩です。
しかし、ただ知識を詰め込むだけでは、理解の深さには限界があります。
アウトプット、すなわち得た知識や経験を他者に伝えることで、
初めてそれが自分の「実感」として深く根付きます。
具体例1 海外での起業経験を通じて得た学びとその伝達
私は20代で日本を飛び出し、異文化の地で事業を立ち上げました。
私が起業したあるアジアの国では、経済や価値観が日本とは異なり、
特に組織文化において、従業員は自らの意見を述べたり、
創意工夫を重視する文化が根付いていませんでした。
完全な指示待ち型で、よく言えばトップダウン型の働き方が根付いていました。
そのため、リーダーとしては異なるアプローチが求められることを学びました。
例えば、日本でよく見られる
「共通の目標に向かってチーム一丸となり、協力し合う」というスタイルは、
メンバー全員が自主的にアイデアを出し合い、
それをベースに業務改善を行うことを前提としています。
このスタイルでは、全員が自分の役割を理解し、
チームの目標に向けて積極的に発言・行動することが重要です。
しかし、私がビジネスを行っている国では、一般的に上司の指示に従うことが優先され、
自主的な発言や提案はあまり奨励されていません。
そのため、私がメンバーに「みんなで考え、より良い方法を探りましょう」と促しても、
メンバーが困惑した表情を浮かべたり、具体的な指示を待つ傾向が見られました。
そこで、「共通の目標を持つこと」を重視しながらも、
その目標に向かってチーム全員が動きやすいように、
より具体的で分かりやすい指示を出すようにしました。
たとえば、会議や日々の業務指導において、
単に「この仕事を達成しよう」という大まかな指示を出すのではなく、
「この業務をいつまでに、どの手順で進めるか」「必要なステップは何か」
といった具体的な行動指針を明確にし、
段階を追って目標に到達する方法を示すようにしました。
さらに、進捗に応じて一人ひとりにフィードバックを行い、
彼らが方向性に不安を感じないようにしました。
このように、現地の従業員にとって理解しやすく、
安心して行動できるような指導を行うことで、
彼らが指示待ちに陥ることなく自信を持って業務に取り組むようになりました。
こうした取り組みを重ねるうちに、
少しずつメンバーの中にも「自ら考えること」の重要性が浸透し、
業務の効率化や改善の意識が生まれてきたのです。
このような細やかなアプローチが、異文化での経営において効果的であることを痛感しました。
このような経験から、数年前より現地の日本人ビジネスマンや大学生に「異文化での経営」と
「異文化での相互理解」をテーマに講義を行っています。
ある講義で「多様性がビジネスの成功にどのように影響するか」を話していた際、
学生の一人から「多様性をどのようにリーダーシップに活かすのか?」と質問されました。
この質問は、私自身が経営の現場で何度も試行錯誤してきたテーマであり、
この答えを出す過程で自分のリーダーシップスタイルについても
改めて考えさせられる機会となりました。
現地の組織文化においては、従業員が自ら意見を述べたり提案をすることは少なく、
従来のやり方に従うことが好まれる傾向があります。
しかし、リーダーとしてそのまま受け入れるのではなく、
それぞれのメンバーの特性や強みを引き出す工夫が必要だと感じるようになりました。
そのため、メンバーに安心して発言できる場を設け、
少しずつ意見を求めるようにしました。
これにより、少しずつメンバーが自らの役割について考え、
協力的に動く姿勢が見られるようになり、チームとしての力も高まったのです。
この経験を学生たちに共有することで、
私自身も異文化でのリーダーシップの在り方について再認識する機会になりました。

具体例2 大学院での研究が促す自己反省と自己理解の深化
現在、大学院で経営に関する研究を行っており、
ビジネスの理論や実践を深く掘り下げる機会を得ています。
特に、経営に関するレポートや論文を執筆する中で、
単なる知識の蓄積ではなく、自己の思考や意思決定を見直し、
過去の行動に対して新たな視点での洞察が得られることを実感しています。
こうした分析作業は、日々の経営に忙殺される中ではなかなかできないものであり、
私にとって極めて貴重な時間となっています。
たとえば、ある課題で「意思決定のプロセス」について理論的に研究する機会がありました。
その際、私は過去の自社の経営判断を事例として振り返り、
自分がどういった価値観や目標のもとで判断を下したのかを再度見直すことにしました。
10年前、私の会社で大規模な方針転換を決断したことがあり、
その意思決定の過程を改めて分析しました。
当時、競争が激化していた業界で、短期的な利益を求めることもできた状況でしたが、
私が選んだのは「長期的な成長戦略」でした。
この決断には、当時は直感や経験に頼っていた部分がありましたが、
現在の視点から見ると、
長期的なビジョンと持続可能なビジネスモデルを基盤に置いたものであったことが明確に理解できました。
この分析によって、自分の意思決定の背景には、
目先の利益よりも会社の持続的な成長を見据えた考え方が根底にあったことに気づかされました。
さらに、この研究を通して、
私の意思決定が現在の会社の基盤や文化に大きな影響を与えていることを再認識しました。
例えば、この方針転換によって従業員にも「長期的視野で物事を考える」という価値観が浸透し、
会社全体が短期的な利益追求に固執せず、持続的な成長を目指す文化が醸成されたのです。
こうした発見は、理論を学ぶだけでは得られないものであり、
自分の過去の行動を客観的に振り返ることでしか得られない深い気づきでした。
また、研究を通して得た知見をレポートにまとめ、他者に伝えるプロセスでは、
自分の思考を論理的かつ整理された形で表現するスキルが養われ、
アウトプットの意義を再確認しました。
特に、実体験をもとに理論的に自分の考えを構築し、それを論理的に伝える作業は、
単に知識を蓄積するだけではなく、自己の理解を深め、さらなる成長を促す重要なプロセスです。
このように、大学院での学びは、経営の実務に新たな視点を与え、
私のリーダーシップや意思決定の質を一層高めることにつながっています。
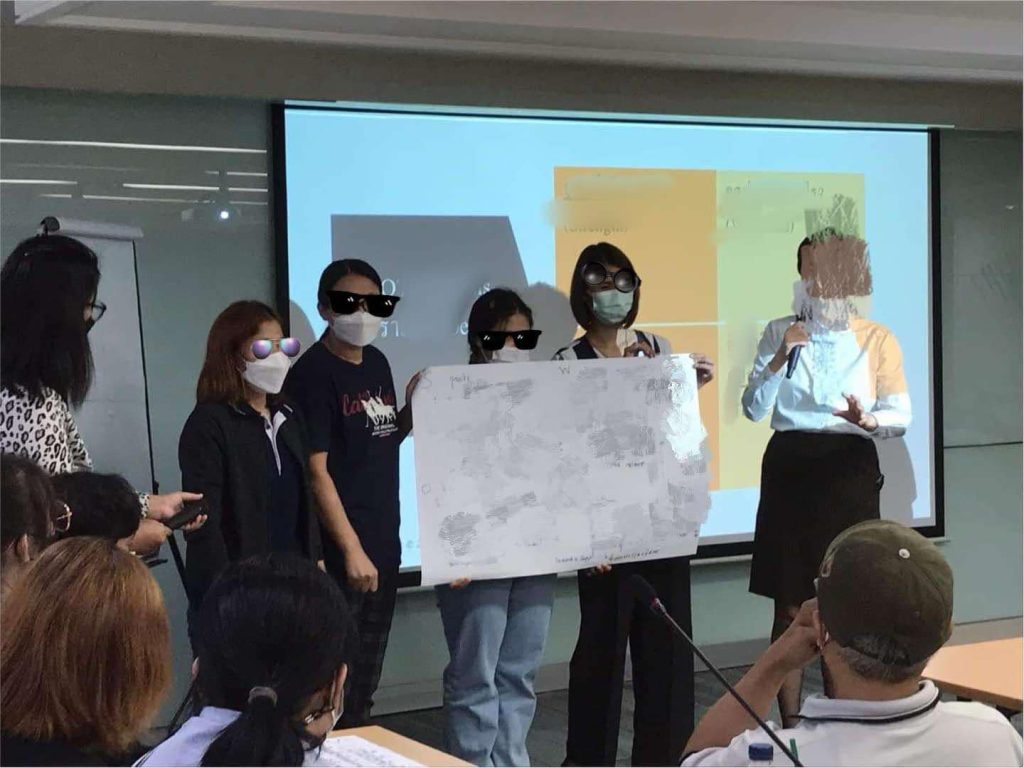
具体例3 異文化コミュニケーションの講義で得た新しい視点
現地の大学で「異文化コミュニケーション」について講義を行っており、
これも自分にとっては大きなアウトプットの機会です。
特に異なる文化背景を持つ学生とディスカッションを重ねることで、
自分の知識や考え方が試され、より多面的な理解へと広がっています。
例えば、「リーダーシップにおける文化の違い」についてディスカッションした際、
アジア圏出身の学生から「リーダーは指示を出すべきだ」という意見がありました。
一方で、欧米圏出身の学生は「リーダーはサポーターであるべきだ」と述べ、意見が対立しました。
実際に私がビジネスを行っている国は
「リーダーが指示を出すべきだ」という考え方が一般的です。
この対話を通じて、
リーダーシップには文化によって異なる期待があることに改めて気づかされました。
私自身も異なる国で経営をしているため、
異文化に対する理解をさらに深める貴重な機会となりました。

アウトプットの効果を最大化するためのポイント
インプット(=経験や学び)を本当の意味で自分のものとするためには、
次のようなアウトプットの実践が効果的です。
自分の理解を深める最良の方法は、得た知識や経験を他人に教えることです。
教える過程で、質問に答えたり具体例を挙げたりすることで、知識が整理され、自然と深まります。
大学院での研究やレポート作成が示すように、
自分の経験や思考を再検討し、文章化することで、
より深い理解や新しい視点が得られます。
ブログなどもおすすめですね。
異なる文化の背景を持つ人々との会話やディスカッションは、
既存の考え方を再評価する良い機会です。
多様な価値観と触れ合うことで、新たな知識や気づきが得られます。
まとめ
インプットはアウトプットによって真の理解へと変わる。
アウトプットの場を積極的に設けることで、学びが一層深まり、実際に役立つ知識が身につく。
今日は
『経験や学びを人生に生かすには?/アウトプットの重要性とその実践方法』
をお伝え致しました。
今日の記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
